
「アンリ・ジャイエのワイン造り」を読んで カテゴリー:本・テレビ 2012-05-22 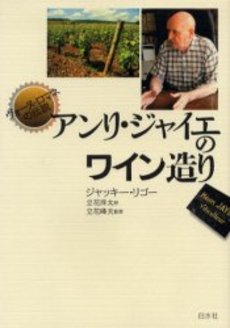
日本では2005年に訳本が出版された。以前から気になってはいたが読む機会に恵まれなかった本だ。
もう余りにも書きたい感想が沢山あり過ぎて、何から書いたらいいか迷ってしまう。
■ 市場原理に基づく値付けが可能にしたこだわりのワイン造り
2005年(実際にインタビューが行われたのは、きっと2003年前後だろう)という時代は微妙だ。あらゆるものがグローバル化する中で、合理化・効率化が急スピードで進むまっただ中にあったはずだ。
手摘みで収穫し、不適格な房は捨て、傷つかないように少量しか入らない箱で運び、発酵は自然に任せ、新樽100%で熟成したワインは飲み頃になるまで年月を要する。どれを取っても非効率なアンリのワイン造りは、昨今の経済原理や経営学から見れば時代に逆行している。
もしワインが、品質や伝説?や格付けによってプレミアム価格で取引される種類の商品でなかったら、アンリのようなワイン造りは許されないはず。そう考えると、芸術的なワインなら高価格でも買ってくれた顧客と、それを後押しした数々の伝統文化に感謝せねばならないだろう。だからこそ、現在も大枚はたいていいワインにお金を投じる人々がいるのだから。
■ 点数には反対のアンリだが点数に支えられているのもアンリ?
ワインを点数で評価することに断固反対の意思を示すアンリ。ひとつには、ワインとの出会いは一期一会であり、同じ条件で出会う機会なんてないからであり、次に人間の感覚がそれほど正確ではないからであり、3つめには評論家たちのテイスティングの仕方が十分にワインを味わえる条件にないからである。なるほど、その通り、彼の主張は正しいと思う。
しかし、評論家の採点や彼らによる新しい注目ワインの発見と情報発信は、手間暇かけてワイン造りをできる可能性を与えてくれていることも確かである。まあ、もちろん、評論家たちが高評価を与えるワインを小手先で造らせるという副作用もあるんだけれど・・・。アンリはその副作用の方を恐れている。
今回はこの辺にしておいて、また回をあらためて感想を書くことにします。では!

明石家さんまの素直なワイン評 カテゴリー:本・テレビ 2012-01-23 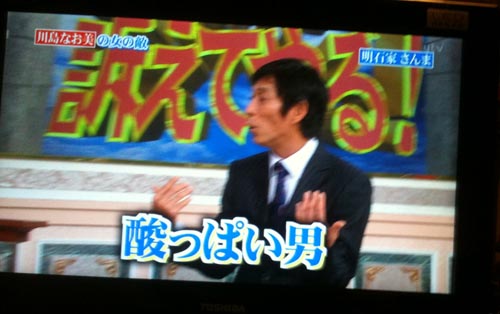
昨日の「行列のできる法律相談所」は、明石家さんまが司会でし
たね。ご覧になった方も多いのでは?
この番組を見て、さんまさんの凄さを認識しました。オモロイ!
そして伸介さんの毒のある笑い取りとちがい、さんまさんは憎た
らしいことを言っても明るいし可愛く感じる。それがスゴイです
ね。
■ロマネコンティ 1955に「酸っぱい」のヒトコト
番組の中で、川島なお美がさんまさんを食事に誘い、1955年、つ
まりさんまさんの生まれ年のロマネコンティを用意していたとい
う話題が取り上げられました。
そして、それを飲んだ時のさんまさんの感想が「酸っぱい」のヒ
トコトだったというお話。川島なお美は、その言葉にひどく傷つ
いたというのです。
1955年はブルゴーニュにとってあまり良い年ではないようで、し
かも2~3年前の話と言いますから、50年以上も経過したモノで
すから、それが美味しいとしたら、よっぽど運がいいケースしか
無いだろうと思われますので、「酸っぱい」という感想はとても
素直なものだっただろうなあと思います。
格好をつけずに「酸っぱい」と言ってしまうさんまさんに好感が
持てました。
■古酒は難しい
今まで私も50年くらい経った古酒を飲む機会がありました。幸運
にもお世話してくださる方のご努力でさすがに「酸っぱい」もの
には遭遇していませんが、だいたい色は褐色になっていて、褐色
になっているということは即ちタンニンが酸化したということな
ので、パワーはなくなっていました。
ボルドーの良いものなら、30年くらいは平気だと思います。40
年、50年となると、まあ避けた方が正解か? というのが私の感
覚です。
ってことで、古酒にはご注意を!

ソムリエ林基就さんの番組を見て思ったこと カテゴリー:本・テレビ 2012-01-04
イタリアで活躍する林基就さん。2009年10月 レストランガイドブック『イ・リストランティ・ディタリア』の最優秀ソムリエを
受賞された方だそうです。
■ワインの香りや味の表現について考えさせられた
彼を特集したテレビ番組を見ました。すごいですねえ。
ワインの香りを表現するために、市場へ出かけてあらゆるモノの香りを嗅ぎまくっておられました。やはり、そんなふうにしないと、他のものになぞらえて香りを表現することは難しいですよね。
いろいろな方や、生産者の方がワインの香りや味について○○や△△の香り・・・などと表現しておられますが、いつも考えさせられてしまうのです。オレンジとか、グレープフルーツ、いちごなど身近なものの香りは私でも想像がつくのですが、書かれてもわかんない表現も沢山あります。
スパイスあるいはスパイシーという表現はあまりにも広く、だってスパイスにはいろいろあるじゃないですか。あと、麦藁のようなという表現も都会育ちの人間にはわかりにくいし、結局お書きになっている本人が記録するためとか記憶するために書かれるのは良いのですが、他人に伝えるには誰もが知っている香りでないと伝わらないのですよ。
■「アルミの味がしますね」と言って変な顔をされた
昔、私が上のような表現をしたら、周りの人がイヤな顔をしました。ミネラルが・・・なんていう人がいますけど、ミネラルもスパイスと同じで沢山あるわけです。アルミニウムなのか、銅なのか、それによって味はちがいます。
このケースも、それぞれのミネラルがどんな味かを知っていないと他人には伝わらないので、香りのケースと同じことです。
そう考えると、他のものに例えて香りや味を表現するのは、とても難しいのです。いくら自分があの香りと思っても、他人に伝わらない表現だと意味がないのですから、表現の幅はうんと狭まり、それでは正確に伝えることもできないということになります。
■最高に開いた状態でサービスする
林さんは、ワインが最もおいしく飲める状態、すなわち「最高にワインが開いた状態」でサービスすることを信条としておられる
とのこと。当然といえば当然なのですが、なんか納得しちゃいました。
まあそれにしても、日常生活でワインを飲む時は、プロの方にそうやって準備してもらうわけではないので、開栓してから変化していく様子を確かめながら楽しむというのが良いようです。
|
タイトルINDEX (本・テレビ)
2012-05-22
「アンリ・ジャイエのワイン造り」を読んで
2012-01-23
明石家さんまの素直なワイン評
2012-01-04
ソムリエ林基就さんの番組を見て思ったこと
カテゴリーINDEX
ワインの成り立ち (17)
造り手・ワイナリー (9)
ワインと料理 (15)
ワインの科学 (9)
ワインショップ (27)
ワイン周辺ツール (4)
レストラン/ワインバー (19)
本・テレビ (33)
データ分析 (19)
ワイン以外のお酒 (6)
その他 (118)
|
![]()
![]() ようこそゲストさん! ログイン
ようこそゲストさん! ログイン