
週刊文春の表紙がフランスワイン地図だ CATEGORY:その他 2011-11-17 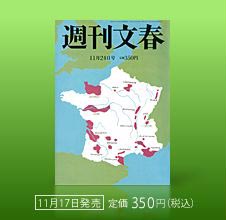
なーんか見慣れた地図だわ~。と思ってじっくり見たら、今発売中の週刊文春の表紙がフランスのワイン地図だったのです。
へーこんなもんでも表紙になるんやねえ。
作者の和田誠さんはとくにワイン通というわけでもないようで、やっぱりボジョレー・ヌーボという季節の話題に触発されてこの絵を描かれたとか。。
しっかし、こんなの、まずフランスの地図と分かる人は1割もいないだろうし、和田さんは絵として面白いと思われたらしいけど、フランスにもワインにも興味のない人が見たら、どう感じるのでしょう? 聞いてみたい気がします。
宣伝になるから、表紙の写真は無断で掲載しました。悪しからず!

堅いことは言いたくないが、料理とワインが合わない! CATEGORY:料理とワイン 2011-11-09 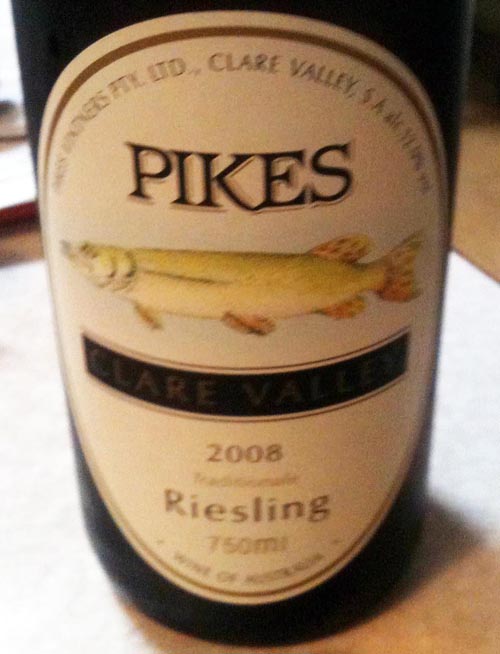
■マリアージュなんてあまり気にする方ではなかった私
「ワインと料理のマリアージュ」とかしたり顔で述べる気持ちはさらさらなく、日頃家で飲むワインは、家庭料理に合うもの、具体的には、白ならドライなもの、赤ならミディアムボディで十
分、泡モノは何でもOKみたいな感じで、事なきを得ていました。
つまり、それほどマリアージュを気にしなくても、料理もワインも美味しくいただけるというのがあたりまえの生活をしていました。
例外としては、経験のある方も多いと思いますが、お正月に数の子でワインを飲むと最悪というのは強烈に記憶に残っています。
■昨日飲んだリースリングと和食の相性が最悪
そんな調子で昨日も母親が作った和食に白ワインと思って、PIKESのリースリングを開けました。
料理は、いさきの煮付け、焼きなす、味噌汁、豚の角煮でした。
まず、先にワインだけ飲んで、エキスが濃くていい感じのリースリングだと思い、次に料理を口にすると、豚の角煮以外は料理の味が薄く感じます。それだけでなく我が家自慢の味噌汁が不味く感じるのです。えー? 何これ? という感じで再びワインに戻ると、ワインは美味しいのです。
でまた、料理に戻ると、料理はダメ。
冷静に考えると、料理に対してワインが強すぎたということになるんですが、たしかにそこそこしっかりした白ワインではあるものの、そこまでのパワーがあったのでしょうか?
常日頃こういう経験があまりないだけに、またひとつテーマを見つけてしまったという感じです。今後、和食とリースリングを意識しながら飲んでみたいと思いました。

ワインを使った料理も奥が深い CATEGORY:ワインと料理 2011-11-06 
■隠し味に使うなら何でもいいが、メインで使うなら飲んでおいしいワインでないとダメ?
今回、イマイチだったワインで、牛すね肉の赤ワイン煮込み(写真)を作りました。このワインの私の評価は5点。でもまあ5点だから料理なら十分だろうと思ってたのですが、そうでもなかったですね。
使ったワインの量は500ml程度で、牛すね肉は阪急オアシスで塊でわけてもらった和牛の300g分です。ソース用の野菜はたまねぎとニンジン。セロリがなかったので、スパイスのセロリーシードを使用しました。
煮込む時にはキューブブイヨンと塩コショウ、多少のスパイスを使用し、トマトジュース200gも入れました。
このレベルでは酸味が勝っていて、味に丸みが足りないので、カシスジャムを足して味を調整する必要がありました。
ワインが美味しくなかったとき「料理にでも使うしかないな」なんて思うのですが、料理に使うのも結構難しいものですね。
■タンニンはすごさは初体験
塩コショウした牛肉を赤ワインに漬けて1日置いたのですが、密閉容器の蓋を開けた時、びっくりしました。
こんなに肉がタンニンで真っ黒になった経験は初めてです。今までもっと安ものの?ワインでしか作ったことがないので、こんなに真っ黒にはなったことがありません。
その色を見て、ちょっと期待したのですが、色だけだったみたい。
■甘みのためにはもっと玉ねぎを使うべきだった?
今思えば、もっとソースに使う玉ねぎの量を増やし、よく炒めて使えば甘みが補えたかと・・・。やはり生半可では美味しい料理は作れませんね。
使用するワインの味をみて、料理の作り方を変えられるようになったら一人前ですね。

ブレンド VS シンプル&ピュア CATEGORY:ワインの成り立ち 2011-10-28
加工される食べ物・飲み物には、常にこの「ブレンド VS シンプル&ピュア」という美味しさの追求方法の2方向が存在しますね。ワインももちろんそうです。
■ブレンドのメリット
何種類かを混ぜると、味も香りも複雑になり、人の感覚はそれを深みとか奥行きと感じます。例えば1種類のぶどう品種では酸味が足りないとか、甘みが足りないとか、欠けているものがあるの
で、異なる性格を持つ品種を混ぜ合わすことで、欠点を補い合うのですね。悪く言えば混ぜてごまかすということなんですが、良く言えばブレンドの妙と言えるでしょう。
木の樽で熟成させるのも、樽の香りや木のエキスが混じることで、複雑さを増すことができるという意味で、ブレンドに似た働きがあると言えます。
ボルドーの有名銘柄は、複数のぶどう品種で造った原酒を最終的に混ぜて完成するので、ブレンドタイプの代表です。
■シンプル&ピュアのメリット
単一のぶどう品種で、しかも樽熟成を行わない(場合によっては畑も1カ所に限定)のが、究極のシンプル&ピュアな造り方ということになります。ぶどう本来の美味しさをそのまま引き出した
ワインということですよね。
しかし、単一のぶどうから最終的にバランスのいいワインを造り出そうとすると、ぶどうの栽培がものすごく重要になってきます。良い土壌、気象条件、土地の手入れや施肥、木の樹齢や剪定、そして適切なタイミングでの収穫。
シンプル&ピュアは、飲む側にとってはぶどう本来の美味しさを楽しめるというメリットがあるものの、造る側にとっては大変な苦労だということになります。
ブルゴーニュはピノ・ノワール100%など単一品種のワインが多いですが、樽熟成はやっているものが多いので、完璧なシンプル&ピュアではありませんが、ボルドーに比べるとシンプルだと言え
ます。
■おそらく現代の食に合うシンプル&ピュアワイン
食品の輸送・保存技術が発達した現代の料理は、素材そのものの美味しさをシンプルに楽しめるものになっています。日本料理などは元々がシンプルですし・・・。
そんな現代の料理には、あまり複雑で強い味のワインは必要ないんじゃないかというのが、私の思うところです。
伝統的で良いものも素晴らしいとは思いますが、どんなものも時代の変化に合わせて変わるものです。
1855年の格付けなんて、100年以上も昔の話ですから、もうそろそろそんなものに引きずられるのはやめてもいいのではないでしょうか?

日本のワインは日本の縮図かも知れない CATEGORY:造り手・ワイナリー 2011-10-19 
当然といえば当然です。どんなものでも、その国を映しているものなんでしょう。
■日本人の真面目さや優秀さを感じるワインもあれば、日本人の浅はかさを感じるワインもある
私はあまり国産ワインを飲んだことがありませんでした。このサイトを始めて、やはり国産ワインも勉強しておく必要があるだろうと思い、少しずつチャレンジしています。
結果、ひどいのもあれば、なかなか頑張ってるなあというモノにも遭遇しました。
まだまだ経験不足であり、この時点で評論するのははばかられるのですが、あえてこの時点で自分がどう感じたかを記録しておくためにも、あえて書きます。
まず、ワイナリーを営利企業として単体で営んでいるところのワインは、それなりに頑張っておられるという印象です。
直近で飲んだ「北海道生ワイン ナイヤガラ」は、甘いのが私好みではなかったけれど、安いし美味しいワインでした。日本人の真面目さや優秀さを感じました。
一方、アルコール飲料を多方面で扱う比較的大きい企業が提供するワインは、ハイエンドの商品は価格がかない高く、まだチャレンジできていません。安い量産品は、どうもダメみたいです。うまく書けないのですが、利益優先プラス流通力で勝負という感が否めません。もちろんビジネスなので利益は大事だし、流通力も大事なんですが、力でねじ伏せているように感じられます。大企業は切羽詰まればもっといい仕事をできる潜在能力はあるだろうと推察しますが、現在のところ未だ目覚めていないように感じます。
■人件費が高く土地が狭い日本は辛い
今更くどくど書く必要はないでしょうが、日本ほどワイン造りに不向きな国もないでしょう。
ニュージーランドでワイン造りが拡大しつつあるようですが、ニュージーランドは日本よりはるかに人口が少ないので、国全体の面積はそう広くなくても、土地的には余裕があります。
中国などは人件費は安いけど、農地には案外恵まれていないといいます。砂漠化を食い止めるためにぶどうを植えるなら、一石二鳥かも知れませんが、実情はどうなんでしょうか? また別途調べてみないといけませんね。ただ、最近の中国では国産ワインの生産が盛んになり、フランスから技術者を招いてがんばっているようです。
日本に話を戻すと、人件費などを勘案してワインの売値を決めると、どうしても価格が高くなってしまいます。安い外国産ワインと戦わねばならないわけですから、他の産業と同様に円高がすすめば国産ワインの割高感は拡大します。
■それでも国産ワインで成功する道はありそうだ
2~3日前に日本ヒューレットパッカードが、パソコンの生産を国内に戻したという記事が掲載されていました。人件費が高く、その他のコストも高いのに、国内生産の方が利益が出るというのです。法人ユースに絞り、オーダーにこたえてカスタマイズするので、発注から納品までの日数が国内でやった方がはるかに早く、効率が良いからだといいます。
この例をヒントにすると、何もボルドータイプの価値観に縛られず、ぶどうを原料としたお酒で、どうやったら競争力のある商品が造れるかを考えたら、まだまだできることはありそうです。
どんなものでもそうですが、外国の文化を真似ることから始めて、自国流のオリジナルでかつ優れたモノを創り出すまでには試行錯誤があるはずです。今までは真似ることに必死だったかも知れません。そろそろ真似から抜け出し、発想を変えたら、もっと日本国民が喜ぶワインができるんじゃないでしょうか? いや、既にそういう方向で成功しつつあるワイナリーもあるのかも知れません。
私も、もっと国産モノを飲んでみたいと思います。
|
TITLE INDEX
2011-11-17
週刊文春の表紙がフランスワイン地図だ
2011-11-09
堅いことは言いたくないが、料理とワインが合わない!
2011-11-06
ワインを使った料理も奥が深い
2011-10-28
ブレンド VS シンプル&ピュア
2011-10-19
日本のワインは日本の縮図かも知れない
2011-10-13
5大シャトーくらいは登録しとこう!
2011-10-11
酸化防止剤無添加表示の流行とマスプロダクツ
2011-10-01
「びっくりするようなワインはありますか?」
2011-09-19
丹波ワインのワイナリーへ行ってきました
2011-09-11
観光と言う名の甘い蜜 KOBEワイン
CATEGORY INDEX
ワインの成り立ち (17)
造り手・ワイナリー (9)
ワインと料理 (15)
ワインの科学 (9)
ワインショップ (27)
ワイン周辺ツール (4)
レストラン/ワインバー (19)
本・テレビ (33)
データ分析 (19)
ワイン以外のお酒 (6)
その他 (118)
|
![]()
![]() Hello. Login
Hello. Login