
青ピーマンの香 カテゴリー:その他 2017-04-25 
昨日飲んだRosso dei Notriという赤ワインは、まず慎重に飲む前にその香り(アロマ)を聞いてみた。
うーん、これって青ピーマン? そう、例えるなら、自分が認知している限りでは青ピーマンというのが最もピンと来る形容だ。
「ワインを楽しむ58のアロマガイド」の“青ピーマン”のところを見ると、青ピーマンという表現は、黒ぶどうのカベルネ・フランやカベルネ・ソーヴィニヨンの香りの特徴となっているという。
ちなみにこのRosso dei Notriはサンジョヴェーゼ主体で、カベルネ・ソーヴィニヨンは20%のようだ。
実際このワインのファーストアタックの香りは、<美味しい赤ワイン>を連想させるものだ。おそらくそれは、今までに飲んだ美味しい赤ワインで経験があったからだと思う。

「ワインを楽しむ58のアロマガイド」 カテゴリー:本・テレビ 2017-04-13 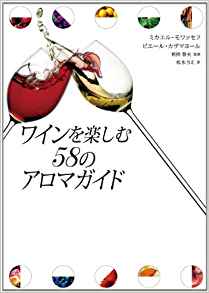
直木賞と本屋大賞をダブル受賞した「蜂蜜と遠雷」を買うために、久しぶりに本屋へ足を運び、そのついでに買ったのが表題の本です。ミカエル・モワッセフ、ピエール・カザマヨール著、松永りえ訳。
アロマを言葉で表現するのが、私の最も苦手とする分野であることは、このコラムで何度か書いたことがあります。というのも、柑橘系とかリンゴといったフルーツ系の香りは、日常よく遭遇する香りで分かりやすいのですぐに表現できるのですが、花の香りとなると、日本人、それも都市生活をしている日本人にとって身近な花の香りといえば、庭や街路樹として生えているキンモクセイや沈丁花、生け花などで接触する機会のあるバラくらいなものです。我が家には幸い庭があり、現在はフリージアが香りを発散しており、他に柊なども強い香りを放ちます。スミレも勝手に生えてきますが、スミレの香りを感じた事はありません(以前、スミレのエッセンシャルオイルをわざわざ買った話を書きましたね)。スズランもいい香りがしますネ。でもここに出てきた植物のうちスミレ以外はあまりワインのアロマの表現に使われることがないようです。
チョコレート、タバコ、松脂といった表現は分からない事もないのですが、それって樽によるところが大きいのではないかと思うと、そうした表現を使う気になれないのです。
表題の本は、専門的かつかなり科学的に書かれているところが気に入りました。
この本からの発見などは、おいおい書いていくとして、58のアロマのうち1番に出てきたアカシアのところで初っ端から挫折してしまいました。実は数年前の6月初旬、私は車で長野県を走りました。その頃はアカシアの花盛りで、高速道路を1時間くらい走っている間中ずっとアカシアが咲いているのが見えていました。ところが残念なことにアカシアの香りを実感せずに帰ってきてしまったのです。なので私はアカシアっぽい香りを放つワインに遭遇しても、それをアカシアと表現できません。
とにかくワインの香りだけで1冊の本というのを私は初めて手にしたので、とてもワクワクしています。

これがカリフォルニアスタイル? カテゴリー:レストラン/ワインバー 2017-04-11 
神戸にフレッド・シーガルがこの3月にオープンした。代官山・横浜に次ぐ3号店とのこと。旧居留地のレトロビル・商船三井ビルにあるこの店の2階には、他2店にはないワイン・レストラン「The Cellar at Fred Segal」があるのです。
1階のセレクト・ショップは、全体的にはとてもカジュアルで、お洋服の他、食器やアロマキャンドルなども売られていて、不思議な事にシャネルのユーズドのバッグなども売っているのです。Tシャツに綿パンといったカジュアル・ファッションにシャネルを合わせるというのがカリフォルニア的おしゃれなんでしょうかね? 私はファッションの世界には疎いのでごめんなさい。
さて、ザ・セラーの方もそういう意味では似通っていて、フードの方は比較的安いお値段なのに、ワインの品ぞろえはなかなか高価なものもあります。というか、平均的にかなり高価格といえます。SCREAMING EAGLEの73万円というのが最高価格だったと思います。
私たちはそんなお金持ちじゃないので、1万円以下でとリクエストしたわけですが、流石にセレクトショップだけあって?美味しいカリフォルニア・ワインを揃えておられると感じました。けど少し割高感ありですねえ。
お店のインテリアなどはとてもスタイリッシュで、おしゃれすぎて気後れ~と、いっしょに行った友達が叫んでいました。
話の種に訪問してみてください。

ヤマザキを目指す外国人たち カテゴリー:ワイン以外のお酒 2017-04-06 
大阪駅はいつも外国人旅行客であふれている。特に今ごろの桜の時期は国籍の多様性も増し、加えて春休みの日本人観光客も多く、毎日がお祭りのようだ。
そんな中、困っている来訪者を目にして、時々私から声をかける事があるんだけれど、ここ1週間ほどで気が付いたのが「ヤマザキ」へ行こうとする外国人が大阪駅のプラットホームで困っているケースが結構あるということだ。
「ヤマザキ」、つまり、サントリーの山崎蒸留所が外国人の注目を集めているらしい。何でも2003年に『インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ(ISC)』のウイスキー部門でサントリーの山崎が金賞を受賞したころから外国人が注目し始め、昨今のSNSコミュニケーションの効果もあって、どんどん山崎蒸留所への来訪者が増えているらしい。
大阪から山崎へ行こうとすると、大阪駅から快速に乗る必要がある。ある日、若い東南アジア系の男性3人連れがスマホ片手に京都行きのプラットホームで困っていた。「京都へ行くの?」と聞いたら、「YAMAZAKI」というので、私は困ってしまった。私は山崎へ行ったことが無い。確か、新快速は山崎には止まらないし、普通電車は高槻までしか行かないから、快速に乗るしかないはず。ところがその日は電車が遅れていて、電光掲示板に快速が表示されていない時間帯だった。それで彼らは困っていたワケだ。「Rapidに乗りなさい。S.Rapidはだめよ」と言ったけど、わかったかなあ?
その次の日も、ヨーロッパ系の若い男性が、その辺にいる人に「ヤマザキ? ヤマザキ?」と聞きまくっていた。
電光掲示板で英語表示される時間は2秒しかない。日本語表示は6~7秒くらいか? たった2秒で読み取れるわけがない。この件は以前からおかしいと思っていて、一度駅員さんにアドバイスしたが、無視された。
もう一つ、山崎事件で気が付いたのは、英語表示で快速=Rapid、各駅停車=Local、新快速=S.Rapidと表示される。この「S」は何のSなんだ? スーパーなのか、スペシャルなのか、シンなのか? 調べてきたら、スペシャルが正解だった。
大阪駅は、東京・京都・新大阪・関西空港などへ行く外国人は想定しているが、山崎は想定していないので、駅内の表示だけで外国人が山崎へ行くのはとても難しい。サントリーに言って、サントリーからJR西日本に圧力をかけてもらう必要がありそうだ。

まだ、こんなことがあったのか カテゴリー:その他 2017-04-05 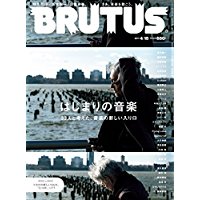
表題は、BRUTUSの最新号の中で坂本龍一さんが語った言葉です。
この前書いたように、dマガジンを利用するようになって、雑誌に接する機会がびっくりする程増え、かつてはBRUTUSなどは美容室で読む程度だったのに、本当にお手軽になりました。
この号は音楽特集です。そして件のお言葉は、坂本さんは普段どんな音楽を聞いているのかという問いかけの中で発せられたものです。
彼はともかくいろんなジャンルの物を雑多に聞くのだそうで、やはり創作面での刺激になると言っていて、そんな中で「まだ、こんなことがあったのか」という発見があるというのです。
私など素人の目から見ると、音楽も既にあらゆる事がやり尽くされた感があって、メロディにしてももう過去にはなかったメロディを生み出すのは難しいのではないかと思ったりします。とくに長年創り続けている人が新しいものを創り出すのはかなり大変なのでは?
それでも、時々「新しい」と感じられる音楽が生まれるのは、案外、既成概念とか、専門教育とかから距離のある人がさらっと創ったものだったりするわけですね。曲全体が常識外れ過ぎると人はとっつきにくくなってしまうのですが、ちょっとした違和感が入っていると「新しい」とか「個性的」と感じるんですね。
私はワインにおいて、その「ちょっとした違和感」を求めている人間の一人だと自覚しています。
今や、チリでもアルゼンチンでも、南アフリカでも、万人好みの飲み口が良くてそこそこコクのあるワインはゴロゴロありますが、どれも同じような方向を向いているんです。音楽で言えば、どこかで聞いたことのあるようなって感じです。ほぼ毎日ワインを飲んでいると、飽きてくるのです。
ちょっとした違和感、今までに感じた事の無い驚きを生んで欲しいし、バイヤーさんにもそういう視点を持ってほしいと願います。 |
![]()
![]() ようこそゲストさん! ログイン
ようこそゲストさん! ログイン