
隠岐の藻塩米 カテゴリー:その他 2013-10-17 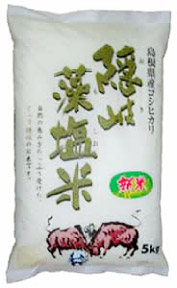
TVで『隠岐の藻塩米』というのを見ました。何でも、藻塩というのは、製塩の際に藻を用いて、何回も藻の上に海水をかけては乾かし、作った塩だそうです。
隠岐の藻塩米は、水田にごく薄い藻塩を混ぜた水を散布して米を栽培しているとのこと。そして島の土壌は第三紀の火山岩質から成るため、海のミネラルと山のミネラルの両方が生かされて、ミネラル分の豊かな美味しい米ができるらしいです。
今まで米についてあまり深く味わい比べたことがなかったですし、米とミネラルなんて、想像したこともなかったのですが、ぶどうと同じく、ミネラルは米の味にも当然影響するのですね。

何だかなあ? 阪急のワインフェア カテゴリー:ワインショップ 2013-10-01 
今日が最終日ということで、筋肉痛で思い足を引きずって行ってきました。
9階催し場までエレベータに乗り、でも9階で降りる人は少ない。フロアも閑散としている。人気がないのかしら?
■ 広範囲な世界のワインを品ぞろえ
ワインと言えば、フランス、イタリア、スペイン、ドイツあたりをイメージするし、大概の場合それらが中心なのですが、今回は、南アフリカ、チリ、アメリカ、グルジア、オーストラリアなど、広い範囲の品ぞろえになっていました。
各ブースのうたい文句も、イマイチよくわからない。現在のワイン事情が曲がり角なのか、企画に問題があるのか。
■ 消極的な売り手
しつこくアプローチされるのも困りものですが、そっけないのもね。
とりあえず主旨がよくわからないので、並んでいる瓶を眺めていても、お店の人はあまり声をかけてこない。慣れていないのか?
たまに声をかけられると「どういうのがお好みですか?」と聞かれる。試しに「香りのいいモノ」とオーダーして進めてくれたシラーのワインは、ぜんぜん香りが良くない。
オーストラリアの泡はまあまあだったが、値段が4000円台。それならシャンパーニュを買うよね!
造り手について聞いてもピンとくる返事が返って来ない。いったい誰をターゲットにしているのでしょう?
■ もしかしてワイン酒場が原因か?
最近増えたワイン酒場。安いワインで気軽に一杯やれるお店である。
そういう店で品ぞろえしているワインは、小売りで1500円以下くらいのものが中心であり、ワインを楽しむというよりは会話を楽しむときのお供がワインという感じなので、あまり品質は重視されない。
一般市民が小売店で買うワインも日常用ならそんなに高いものは無理だ。そんなわけで、値段が安くて味はそこそこというワインが多い。
このフェアでも安いワインが中心で、試飲できるメリットはあっても、品ぞろえはつまらない。
このような催しも、少し考え直した方がいいのではないかと感じてしまった。

古いワイン本の選別 「ブルゴーニュ ~ブルゴーニュワインの決定版ガイド~」 カテゴリー:本・テレビ 2013-09-02 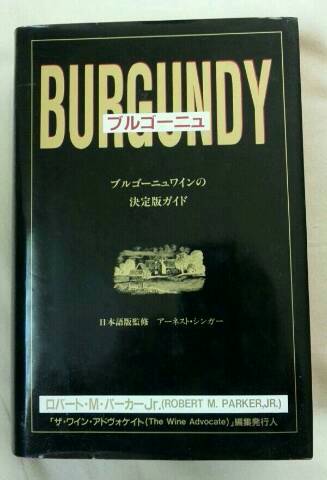
「ブルゴーニュ ~ブルゴーニュワインの決定版ガイド~」
ロバート・M・パーカーJr.著 1992年発行
ボルドーと同様。

古いワイン本の選別11 「ボルドー 1961年以降生産されたワインの決定版ガイド」 カテゴリー:本・テレビ 2013-09-01 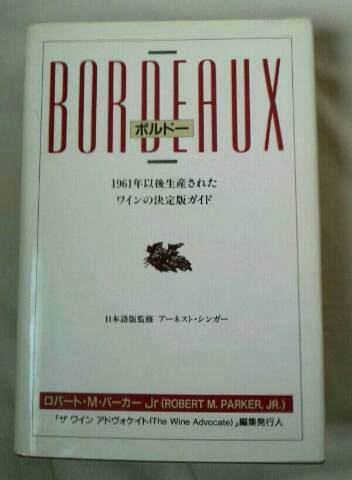
「ボルドー 1961年以降生産されたワインの決定版ガイド」ロバート・M・パーカーJr.著 1993年発行
何と当時5000円もした枕のような本である。
非常に詳しく、収穫年ごとの評価も詳しい。
パーカーさんについては賛否あるところだけど、ここまでしっかり書かれていたら、普通の人は圧倒される。
だが、本当にこんなに沢山ティスティングできるものだろうか? 人間業とは思えない。そこがひっかかるところ。
本来ならば、毎年これを購入するのがプロかも知れないが、そこはそれ私はアマ(海女ではない)ので、この年にしか購入しなかったんだ。
私にとっては一種、歴史的価値があるので、置いておこう。

古いワイン本の選別10 「ワインの話」 カテゴリー:本・テレビ 2013-08-12 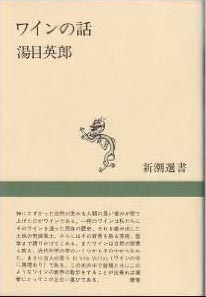
「ワインの話」 湯目英郎著 1984年発行(新潮選書)
著者はサントリーの社員さんである。
私はこの本の内容を本当にぜんぜん覚えていなかった。なぜだろう?
今読むとなかなか面白いのだけれど、おそらく1984年当時は読んでも面白いと思わなかったのではないかと思う。
話は「ワインの起源」から始まる。そして、物語の中に登場するワインの話なども登場する。著者は東大農学部出身だから、発酵等、ワインができるまでの科学にも目を向けていて、そのような記述もたびたび出てくるものの、体系的にこの本にまとめたという感じではない。
日本人がワインというものを理解しようとするときに知る様々なことが書き連ねられているという感じ。
著者や編集者には失礼かも知れないが、もう一つ整理されていなくて、読みづらい本であることは確かだ。ただ、しっかり読めば宝物が隠れているかも知れない。
取り置くか捨てるか、もう一度しっかり読んでから決めようと思う。 |
![]()
![]() ようこそゲストさん! ログイン
ようこそゲストさん! ログイン